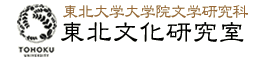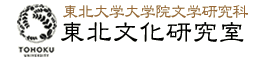東北文化研究室紀要 文献目録 東北文化研究室紀要 文献目録
東北文化研究室紀要通巻第56集(2015年3月)
- 大渕憲一、
伝統的価値観の国際比較
―日本、韓国、中国、米国における仏教的価値観―
- 泉啓・若林真衣子、
仙台市における依存症支援のネットワーク形成史
―T病院と自助グループの協働関係に注目して―
- 小田島建己、
新春のノベルティにおける福祥のイメージ
―岩沼で配布された正月用引札―
- 2014年度 東北文化研究室講演会
- 木村敏明、
東北大学文学研究科発の被災地支援活動
東北文化研究室紀要通巻第55集(2014年3月)
- 小林隆・内間早俊・坂喜美佳・佐藤亜美、
言語行動の枠組みに基づく方言会話記録の試み
- 川口幸大・菊池遼・関美菜子、
被災地のフェーズ変化に対応した遠隔地からの中長期的支援
― 山形から石巻への支援を行う大学生の団体「START Tohoku」を事例として―
- 2013年度 東北文化研究室公開講演会
歴史のなかの東北大学と社会―「門戸開放」と女子学生―
- 講演1 永田英明、
女性たち・留学生たちの学都仙台
- 講演2 柳原敏昭、
女子学生運動事始
東北文化研究室紀要通巻第54集(2013年3月)
- 森谷圓人、
幕末維新期、村・地域社会の民衆運動と高抜地
― 出羽国村山郡の課題 ―
- 2012年度 東北文化公開講演会
表象としての身体―死の文化の諸相
- 発表1 近田真美子・鳴海幸、
死に逝く身体と〈向き合う〉ということ―看取りの現場から
- 発表2 高橋恭寛、
儒礼における埋葬への視線
- 発表3 小田島建己、
〈死体なき墓〉と墓参―宮城県岩沼市の被災墓地
- 発表4 ジョン=モリス、
弘智法印について
- 発表5 菊谷竜太、
インド・チベット密教における死兆と臨終行事
- 講演1 小谷みどり、
埋葬の現場における身体
- 講演2 芳賀京子、
西洋古代における死とその表象
- 講演3 杉山幸子、
死の概念形成と身体
- 講演4 山田慎也、
死絵における死のイメージ
- 柳田俊雄、
日本列島の旧石器時代編年と地域性の成立について
― 東北地方と九州地方の資料群の比較から ―
- アリマンシャル、
竹駒神社の神職にみる清めの意味
- 黄緑萍、
流行神研究序説:
『郷土の伝承』に見られる信仰の諸相
東北文化研究室紀要通巻第53集(2012年3月)
- 大藤修、
仙台藩儒学者芦東山の生涯と関係史料の伝来・構成:
付「芦東山記念館所蔵史料目録」
- 柳田俊雄、
大分県早水台遺跡下層出土石器群と東海地方二遺跡の比較研究
- 内間早俊、
陸羽東線沿線地域における方言音の動態について
東北文化研究室紀要通巻第52集(2011年3月)
- 平川新、
政宗謀反の噂と徳川家康
- 渋谷悠子、
近世墓標・過去帳・系譜類にみる武家の家内秩序と「家」意識
- 森谷圓人、
近世後期、高抜地負高請をめぐる幕府代官所、村と地主集団
― 出羽国村山郡日和田村を事例として ―
- 徳竹剛、
帝国議会の開設と地域有力者
― 岩越線の官設第一期繰上運動を事例に ―
- 茂木謙之介、
地域社会の皇族表象
― 昭和10年代・青森県を事例に ―
- 川越めぐみ、
東北地方の民話に見るオノマトペ後接辞「テ」「ト」の用法
- 田附敏尚、
青森県五所川原市方言における質問の文末形式
― 文末形式「ナ」と「バ」の用法と意味・機能
- 津田智史、
東北諸方言アスペクトの捉え方
- 鹿又喜隆、
細石刃集団による地点間の活動差
東北文化研究室紀要通巻第51集(2010年3月)
- 永井彰、
沖縄の島嶼部における地域ケア・システム構築の現状と課題
- 小田島建己、
奉納のエコノミー
― 〈死者の結婚〉をプロモートするもの ―
- 小林輝之、
戦没者追悼の現在
― 宮城県塩竈市浦戸桂島地区の場合 ―
- 東北文化シンポジウム
死を見つめる心 ― 現代東北の葬送文化 ―
花登正宏、開会の挨拶
研究発表
- 碑文谷創、
現代日本の葬送事情
- 田中則和、
考古学から見た東北地方の葬送文化
- 澤村美幸、
「死」をめぐる言葉 ― 方言学の立場から ―
- 鈴木岩弓、
葬儀社アンケートから見た東北地方の葬送文化
- 山田慎也、
いますがごとくの葬送
― 秋田県男鹿市のある酒造旧家の葬儀と通して ―
- 中西太郎、
東北地方のあいさつ表現の分布形成過程
― 朝の出会い時の表現を中心にして ―
- 大道晴香、
民間巫者の死後における「祭壇」の継承
― 青森県八戸市の事例から ―
東北文化研究室紀要通巻第50集(2009年3月)
- 天野真志、
幕末平田国学と秋田藩
― 文久期における平田延太郎(延胤)の活動を中心に ―
- 梶沼彩子、
松森胤保『止戈小議』考
― 序説・附翻刻 ―
- 『東北文化研究室紀要』目録(創刊号~第50集)付:著者別索引
- 海野道郎、
現代日本の不公平感
― 「仙台高校生調査」における20年の変化 ―
- 菅野智則、
北上川流域縄文時代中期から後期における土器の器形変化と地域性に関する研究
- 阿部友紀、
霊験譚の語りと信者
― 『善宝寺龍王講だより』の事例より ―
- 中西太郎・田附敏尚・内間早俊、
秋田県の言語調査報告
- 澤村美幸、
方言形成と意味変化
― 「スガリ」を例として ―
東北文化研究室紀要通巻第49集(2008年3月)
- 永井彰、
自治体合併にともなう地域経営の変容
― 広島県三次市君田町の事例 ―
- 大坂紘子、
児童養護施設の職員ストレス対処と職員間連携に関する探索的研究
- 金澤悠介、
信頼と社会参加に関する地域比較
― 社会調査による検討 ―
- 高橋雅也、
技術遺産の保存と伝承主体の複数性
― 近代築港事業の一事例から ―
- 東北文化研究室公開シンポジウム
「ゴミの文化学 ― 過去と現在 ―」報告
- 永井彰、
ゴミの文化学:過去と現在 ― 企画の意図と構成について ―
- 菅野智則、
縄文人の「ゴミ」と集落
- 阿子島香、
貝塚・石器・石のゴミ ― 菅野氏へのコメント ―
- 松井章、
古代都城の廃棄物処理 ― 平城京・平安京を中心として ―
- 今泉隆雄、
都市空間の成立とゴミ問題の発生 ― 松井氏へのコメント ―
- 海野道郎、
ごみ排出行動にみる利害と理念
- 安田八十五、
都市自治体のごみリサイクル政策に関する課題と評価
― 海野氏へのコメント ―
東北文化研究室紀要通巻第48集(2007年3月)
- 加藤諭、
昭和初期東北地方における百貨店の催物
― 三越仙台支店、藤崎を事例に ―
- 高橋雄七、
武士身分の入寺
― 秋田藩所預佐竹南家を例として ―
- 天野真志、
文久・元治期における秋田藩の情報政策
― 京都・江戸との関わりから ―
- 小田島建己、
若松寺にみる「ムカサリ絵馬」の展開
- 大坂紘子、
中高年女性ボランティアのライフイベントと地域ボランティア活動
― 子の巣立ち・親の介護と入会時動機 ―
- 林雄亮、
「格差社会」における社会意識
― 2006年格差と不平等に関する仙台市民意識調査の概要 ―
- 阿部友紀、
漁民と祈祷札
― 善宝寺信仰を手がかりに ―
- 東北文化公開シンポジウム
東北像再考:地域へのまなざし、地域からのまなざし
- 佐倉由泰、
― その概要とこれからの展望 ―
- 山田仁史、
奥羽人類学会と東北の信仰・民俗
- 六車由実、
地域の人たちが地域の文化をみる、そのネットワーク
― 山田発表へのコメント ―
- 柳原敏昭、
東北と琉球弧 ― 島尾敏雄「ヤポネシア論」の視界 ―
- 野口実、
日本中世史研究の現状から「地域」を考える
― 柳原敏昭氏「東北と琉球弧」へのコメント ―
- 高橋章則、
「狂歌」が語る地域の歴史 ― 江戸時代の「大崎」文化 ―
- 鈴木俊幸、
「普通」のこと ― 高橋章則報告の尻馬に乗って ―
東北文化研究室紀要通巻第47集(2006年3月)
- 永井彰、
島嶼地域における高齢者ケアの諸問題
― 鹿児島県甑島列島の事例 ―
- 高橋陽一、
近世後期の川渡温泉
― <史料紹介> 陸奥国玉造郡大口村・藤島家文書(下)―
- 東北文化講演会
国際シンポジウム 「山と神 ― 東アジアの視点から ―」
野家啓一、開会の挨拶
鈴木岩弓、問題提起
研究発表
- 川島秀一、
『遠野物語』の山の神
- 佐倉由泰、
中世日本の山と物語
- 長岡龍作、
山の像 ― 古代日本の山岳観と神仏
- 陶思炎、
石敢当と山神信仰
- 任東権、
韓国の山と神
- 大坂紘子、
地域社会におけるボランティアによる援助活動の実際
― 被援助者の属性・援助内容・援助先への交通手段と移動時間 ―
- 椎名渉子、
あやし表現からみる子守歌詞章の地域差
東北文化研究室紀要通巻第46集(2005年3月)
- 平川新、
ゴロウニン事件と若宮丸漂流民の善六
- 高橋陽一、
近世の温泉史料にみる争論
― <史料紹介> 陸奥国玉造郡大口村・藤島家文書(上) ―
- 海野道郎、
父親の不公平感はなぜ低いのか
― 仙台都市圏における高校生調査データの統計分析 ―
- 三和哲、
学歴意識の潜在構造にかんする日韓比較分析
― 意識調査に見る「学歴社会神話」の現在 ―
- 本間照雄、
高齢者福祉施設における「看取り」の問題
― 宮城県M施設及びS施設の事例から ―
- 琴鐘愛、
仙台方言における談話展開の方法の世代差
― 談話標識の出現傾向から見る ―
- アンドリューズ・テール、
「死」に関わる一家の社会的な関係
東北文化研究室紀要通巻第45集(2004年3月)
- 伊藤大介、
近代日本における地域振興政策の展開
― 北海道と沖縄・奄美の地域振興調査会 ―
- 栗原伸一郎、
幕末期の上山藩と奥羽諸藩
― 上山藩士金子与三郎の思想と行動を中心に ―
- アンドリューズ・デュール、
島守四十八社にみる地域と信仰
― 三戸郡南郷村島守地区の事例から ―
- 作田将三郎、
飢饉資料からみた〈糠〉の東北地方語史
- 大坂紘子、
地域ボランティア活動動機における「故郷」の影響
― ライフヒストリー法による一中高年女性の研究事例 ―
- 武田篤史、
三つの「森の都」と観光のまなざし
― 仙台・金沢・熊本 ―
東北文化研究室紀要通巻第44集(2003年3月)
- 永井彰、
農山村地域における地域ケア・システムの再編成
― 長野県・佐久総合病院の事例 ―
- 竹田晃子、
小林好日氏による東北方言通信調査
- 高橋雅也、
新しい担い手による民俗文化の「復活」
― 郷土史と向き合う過程としての「語り」 ―
- 武田篤志、
観光のまなざしと都市空間の構成
― 観光シティループバス「るーぷる仙台」を事例に ―
- 本間照雄、
敬老会で見る高齢者福祉施設の現状
― 個室ユニットケア型特養「杜の風」の事例研究 ―
東北文化研究室紀要通巻第43集(2002年3月)
- 高橋章則、
『曳尾堂蔵書目録』(半沢久次郎蔵書目録・熊阪台州旧蔵書目録)
― 翻刻と解題 ―
- 松本純子、
近世社会の高齢者比率と「荒廃」下の老人・子供
- 待井扶美子、
墓所有形態にみるキリスト教受容の諸相
― クリスチャンの家族関係を切り口として ―
- 滝澤克彦、
ある山村に見る祭祀空間の構造
― 民俗的「世界観」についての一考察 ―
- 菊池奈緒子、
都市から農村への移住者の社会化過程
― 慣習への対応行動をとおして ―
- 小林隆、竹田晃子、玉懸元、佐藤祐希子、
宮城県石巻市方言の記述的調査報告
東北文化研究室紀要通巻第42集(2001年3月)
- 中嶋隆蔵、
北辰・北斗信仰
― 宮城県北の一神社に論を起こして日本と中国の比較に及ぶ ―
- 永井彰・菅原真枝、
農村家族の変動過程にかんする生活史的分析
― 宮城県亘理郡山元町の事例 ―
- 畑井洋樹、
藩主と側近
― 元禄年間の盛岡藩の場合 ―
- 松本純子、
行き倒れ人と他所者の看病・埋葬
― 奥州郡山における行き倒れ人の実態 ―
- Raphaella D.Dwianto,
The Present Form of Neighborhood Association:
A Study Case on Chonaikai Liaison Group in Morioka Senboku nishi Land Readjustment
- 伊藤辰典、
旧仙台領における修験寺院の変遷〔Ⅱ〕
- 山尾貴則、
インターネット時代の地域情報化
― 長野県諏訪地方の事例―
東北文化研究室紀要通巻第41集(2000年3月)
- 華園聰麿、
東北の霊場 その「まいり」の形と心
― 観音札所巡礼の「納札」の分析を中心として ―
- 森澤眞直、
新古今時代和歌における視点と発語状況の問題
- 伊藤辰典、
旧仙台領における修験寺院の変遷〔Ⅰ〕
- ヤマモト・ルシア・エミコ、
宮城県に滞在する出稼ぎブラジル家族の事例研究
― 労働観、学校教育観を中心にして ―
- 沼崎一郎、
日本の中のフィリピン、フィリピンのなかの日本
― 仙台七夕祭の「多文化化」についての覚書 ―
東北文化研究室紀要通巻第40集(1999年3月)
- 高橋章則、
熊阪台州著 『道術要論』
― 翻刻と解説 ―(2)
- 糟谷和香江、
日系移住地における学校教育の展開
― ボリビアのオキナワ移住地の事例 ―
- 高橋徹・近藤博文・関田康慶、
高齢者の地域生活と社会的ネットワーク
― 秋田県A町の事例から ―
- 小林隆・李範錫・竹田晃子・瀧川美穂、
宮城県仙台市方言の記述的調査報告
- 関根達人、
東北地方における近世食膳具の構成
― 近世墓の副葬品の検討から ―
- 高橋嘉代、
死亡広告に見る人間関係の諸相
- 鈴木岩弓 ・ サンドラ・ヘルリナ、
墓が語る現代(2)
― 仙台市における民営共同墓地の場合 ―
東北文化研究室紀要通巻第39集(1998年3月)
- 永井彰、
農村地域における地域医療・福祉システムの形成と展開
― 長野県小県郡武石村の事例 ―
- 高橋章則、
熊阪台州著 『道術要論』
― 翻刻と解説 ―(1)
- 吉原直樹、
頼母子講の存続形態と機能に関する一事例研究
― アリサンとの比較で ―
- 田名場美雪、
生活記録からエイジングの意味づけを読みとる試み
- 藤沢敦、
仙台平野における埴輪樹立古墳の墳丘と外部施設
東北文化研究室紀要通巻第38集(1997年3月)
- 永井彰、
水稲単作地帯における農村家族の動態
― 宮城県南郷町K地区の事例 ―
- 鈴木拓也、
払田柵と雄勝城に関する試論
- 羽下徳彦、
東北大学文学部国史研究室保管文書(乙類・完)
- 田名場美雪、
個人史と地方史からとらえたエイジングの内面化
― 秋田県北秋田郡合川町「母の実会」を例にして ―
- 鈴木岩弓、
墓が語る現代
― 仙台市営葛岡墓園の場合 ―
- 氏家千恵、
方言談話資料形式による遠野郷の昔話(1)
- 加藤正信・小林隆・大橋純一・竹田晃子、
宮城県中新田町方言の記述的調査報告
東北文化研究室紀要通巻第37集
(日本文化研究所研究報告別巻第33集 1996年3月)
- 高橋美貴、
「処見」・「異見」・「附言」
― 明治10年代『秋田県庁文書』への文書論的アプローチ ―
- 伊藤辰典、
仙台藩における修験寺院の概観
― 『安永風土記』を史料として
- 森幸一・大橋英寿、
日系人移住地への現地労働者の流入と定着
― ボリビアのオキナワ移住地の事例 ―
- 亀田裕見、
福島県相馬地方の無型アクセント多人数話者における音相
― 基本周波数曲線の視覚的パタン分類による ―
- 須藤隆、
亀が岡文化の発展と地域性
東北文化研究室紀要通巻第36集
(日本文化研究所研究報告別巻第32集 1995年3月)
- 佐藤勉・水上英徳、
農業生産組織の存続と変貌
― 宮城県鹿島台町山船越地区の事例 ―
- 末永恵子、
幕藩領主の宗教観と儒者の排仏論
― 仙台藩を事例として ―
- 村瀬洋一・阿部晃士・中野康人・海野道郎、
ごみ処理施設建設政策への仙台市民の政治参加行動
― 自由回答形式非定型データの計量分析 ―
- 鈴木岩弓、
庄内地方における「もり供養」の寺院行事化現象の実態
東北文化研究室紀要通巻第35集
(日本文化研究所研究報告別巻第31集 1994年3月)
- 永野由紀子、
農村家族の変容と農村女性
― 山形県庄内地方の場合 ―
- 小林文雄、
南部藩における芸能興行と権威支配
- 鈴木拓也、
古代陸奥国の官制
- 加藤正信・齋藤孝滋・半沢康・亀田裕見、
福島県小高町における方言の共通語化に関する社会言語学的調査報告
- 氏家千恵、
方言談話資料形式による江刺市米里の昔話(4)
東北文化研究室紀要通巻第34集
(日本文化研究所研究報告別巻第30集 1993年3月)
- 村上雅孝、
近世初中期における朝鮮漢字文化の展開
- 華園聰麿・山崎亮、
都市近郊農村における伝統的信仰の諸相
― 仙台市泉区福岡地区の事例から ―
- 羽下徳彦、
東北大学文学部国史研究室保管文書(承前・結)
- 小松洋・海野道郎、
廃棄物収集システムをめぐる意志決定と住民の対応
― 仙台市における事例研究 ―
- 大橋英寿・杉山幸子・安保英勇、
(資料)東北の巫者・祈祷師〔Ⅳ〕
― 要約と考察 ―
東北文化研究室紀要通巻第33集
(日本文化研究所研究報告別巻第29集 1992年3月)
- 綿貫友子、
中世後期陸奥国における熊野信仰
― 旦那・先達の分布と道興准后の順路に関する覚書 ―
- 羽下徳彦、
東北大学文学部国史研究室保管文書
- 船津衛・高橋征仁、
東北地方の地域情報化政策の現状と問題
- 齋藤孝滋、
岩手県一関市舞川方言の音韻
- 氏家千恵、
方言談話資料形式による江刺市米里の昔話(3)
東北文化研究室紀要通巻第32集
(日本文化研究所研究報告別巻第28集 1991年3月)
- 華園聰麿、
死者・先祖供養における重層性と地域性
― 青森県における地蔵信仰と「イタコ」信仰との関連をめぐって ―
- 中川学、
給人地方知行制下における村落構造の特質
― 仙台藩の「奉公人前」をめぐる問題 ―
- 佐島隆、
死をめぐる伝統的習俗の変容
― 陸中沿岸山田町の事例を中心にして ―
- 加藤正信・村上雅孝・神戸和昭・齋藤孝滋・武田拓・半沢康、
南部・伊達藩境地帯における方言分布調査の報告と考察
- 海野道郎・松野隆則・小松洋・土場学、
地域社会における共有物の管理(2)
― ゴミの分別をめぐる仙台市民の意識と行動 ―
- 氏家千恵、
方言談話形式による江刺市米里の昔話(2)
- 大橋英寿・杉山幸子・安保英勇、
(資料)東北の巫者・祈祷師〔Ⅲ〕
― 山形県・福島県 ―
東北文化研究室紀要通巻第31集
(日本文化研究所研究報告別巻第27集 1990年3月)
- 斎藤吉雄、
日本人の公・私観念
― その基礎構造と国際性 ―
- 松井克浩、
農業経営の合理化と「家」の再編
― 山形県庄内地方の事例 ―
- 海野道郎・松野隆則、
地域社会における共有物の管理
― ごみ集積所をめぐる仙台市民の意識と行動 ―
- 大西拓一郎、
宮城県志津川町方言の用言のアクセント
― 動詞の変化形を中心に ―
- 氏家千恵、
方言談話資料形式による江刺市米里の昔話(1)
東北文化研究室紀要通巻第30集
(日本文化研究所研究報告別巻第26集 1989年3月)
― 特集 日本人の公私観念 ―
- 斎藤吉雄、
日本人の公私観念 ― その理論的考察 ―
- 加藤正信・村上雅孝・三井はるみ・田中牧郎・鎌田真俊、
言語における日本人の公私観念
―文献における語彙調査と水沢市における場面別調査から ―
- 華園聰麿、
信仰の多元性に関する調査報告
― 公私観念との関連を含めて ―
- 田中秀和、
明治初期の国民教化と東北
― 教部省政策と東北の教院体制 ―
- 渡辺浩一、
近世後期における在郷町共同体と藩権力
― 文政七年郡山町昇格をめぐって ―
- 佐島隆、
三陸沿岸漁村における漁業集団に関連する信仰形態について
― 岩手県山田町大沢村の「七こもり」行事を中心に ―
- 船津衛・徳川直人・高橋征仁、
東北地方における地域情報化と地域メディアの課題
- 大西拓一郎、
宮城県北部方言の名詞のアクセント語彙
- 大橋英寿・杉山幸子・安保英勇、
(資料)東北の巫者・祈祷師〔Ⅱ〕
― 岩手県・宮城県 ―
東北文化研究室紀要通巻第29集
(日本文化研究所研究報告別巻第25集 1988年3月)
- 華園聰麿、
明治期における神社政策の経過と影響
― 宮城県の神社関係公文書の分析を中心にして ―
- 永井彰、
水稲単作地帯における農村家族の生活史的研究
― 宮城県南郷町K地区のばあい ―
- 加藤正信・三井はるみ・大西拓一郎・志村文隆、
青森県津軽地方の方言調査報告
- 大橋英寿・南部昭文・安保英勇、
(資料)東北の巫者・祈祷師〔Ⅰ〕
― 青森県・秋田県 ―
東北文化研究室紀要通巻第28集
(日本文化研究所研究報告別巻第24集 1987年3月)
- 佐島隆、
陸中沿岸地域におけるオシラサマ信仰
― 岩手県下閉伊郡山田町の事例研究 ―
- 渡辺英夫、
利根川水運の地域構造
― 利根川中流域を対象にして ―
- 渡辺浩一、
近世後期における在郷町の住民結合
― 日光道中粕壁宿を事例として ―
- 佐藤貴裕、
『下愚方言 鄙通辞』解題・翻刻・研究(二)
- 片瀬一男、
青年期のアイデンティティ・ステイタス
― 東北大学学生の意識調査より ―
東北文化研究室紀要通巻第27集
(日本文化研究所研究報告別巻第23集 1986年3月)
- 佐藤勉・佐久間政広、
農業生産組織の存立と「非受委託」農家の動態
― 愛知県安城市高棚町新池地区の事例 ―
- 加藤正信・佐藤貴裕、
『下愚方言 鄙通辞』解題・翻刻・研究(一)
- 渡辺信夫・荻慎一郎・築島順公、
陸中国下閉伊郡岩泉村早野家文書(下)
- 作道信介、
羊と羊飼い
― S教会におけるアイデンティティの確立 ―
東北文化研究室紀要通巻第26集
(日本文化研究所研究報告別巻第22集 1985年3月)
- 楠正弘、
燃える「シャーマン」
― 「堀シャーマニズム論」をめぐって ―
- 佐藤勉・村田浩志・佐久間政広、
都市化の進展と農業生産組織の成立
― 愛知県安城市高棚町の事例研究 ―
- 渡辺英夫、
利根川舟運の輸送機構
― 上流域の艀下輸送について ―
- 渡辺信夫・荻慎一郎・築島順公、
陸中国下閉伊郡岩泉村早野家文書(上)
東北文化研究室紀要通巻第25集
(日本文化研究所研究報告別巻第21集 1984年3月)
- 楠正弘、
シャマンと憑依
― 柳田の巫女論をめぐって ―
- 羽下徳彦、
中世後期武家の贈答おぼえがき
- ジョン・モリス、
給人地方知行制下における「兵農分離」
― 仙台藩における給人家臣(藩陪臣)の分析 ―
- 作道信介、
宗教集団の発展段階と入信過程
― 宮城県におけるS教会を対象として ―
- 小林裕、
生産労働者のキャリアと意識の変化
― N製靴工場の従業員実態調査 ―
東北文化研究室紀要通巻第24集
(日本文化研究所研究報告別巻第20集 1983年3月)
- 鈴木則郎・呉羽長、
『松嶋日記』考
― その成立と清少納言の晩年 ―
- 平川新、
近世の商品流通と運輸機構
― 信越間交通の展開 ―
- 渡辺信夫・築島順公・ジョン・モリス、
陸中盛岡下閉伊郡穴沢村工藤家文書目録(下)
- 小林一穂・秋葉節夫、
地方都市における「コミュニティ形成」
― 山形県鶴岡市の事例研究 ―
- 加藤正信・小林隆・遠藤仁、
山形県最上地方の方言調査報告
東北文化研究室紀要通巻第23集
(日本文化研究所研究報告別巻第19集 1982年3月)
- 渡辺信夫、
天正18年の奥羽仕置について
- 平川新、
南部鉄の流通構造
― 近世後期の中村屋の場合 ―
- 鈴木岩弓、
「もり供養」の一考察
― 参詣者の意識と行動をめぐって ―
- 渡辺信夫・築島順公・ジョン・モリス、
陸中盛岡下閉伊郡穴沢村工藤家文書目録(上)
- 加藤正信・佐藤和之・小林隆、
宮城県北地方の方言調査報告
東北文化研究室紀要通巻第22集
(日本文化研究所研究報告別巻第18集 1981年3月)
- 志村良治、
「お岩木様一代記」小考
― ものがたりの始源 ―
- 鈴木則郎・呉羽長、
東北大学附属図書館所蔵『松嶋日記』翻刻と注釈
- 荻慎一郎、
南部鉄山における生産組織と労働組織
― 近世後期の中村家の場合 ―
東北文化研究室紀要通巻第21集
(日本文化研究所研究報告別巻第17集 1980年3月)
- 荻慎一郎、
米沢藩寛政改革における農村政策
- 楠正弘・川村邦光、
死者供養の一考察
― 福島県会津地方の冬木沢参りをめぐって ―
- 加藤正信・半沢洋子・佐藤和之、
会津地方の方言調査報告
- 斎藤吉雄・竹内彰啓・片瀬一男、
地域構造とコミュニティーの組織化
東北文化研究室紀要通巻第20集
(日本文化研究所研究報告別巻第16集 1979年3月)
- 楠正弘、
ゴミソ信仰
― 日本的シャマニズムの一形態 ―
- 斎藤吉雄・宇田川拓雄、
都市コミュニティにおける“生活の質”
― 仙台市と喜多方市の比較調査 ―(その1)
- 菊田茂男・呉羽長、
日本古代文芸における東北
― 叙事的作品を中心として ―
- 渡辺信夫・荻慎一郎・鯨井千佐登、
陸奥国九戸郡軽米村淵沢家(屋号元屋)文書目録
東北文化研究室紀要通巻第19集
(日本文化研究所研究報告別巻第15集 1978年3月)
- 渡辺信夫、
近世初期人返令の展開
- 佐藤勉・谷田部武男、
農業生産組織の展開過程
- 深井甚三、
近世中後期の城下町構造の変容と町人層の動向
― 信州上田城下町の場合 ―
- 竹内彰啓、
コミュニティの構造とコミュニティ性
東北文化研究室紀要通巻第18集
(日本文化研究所研究報告別巻第14集 1977年3月)
- 菊田茂男、
仙台時代の北杜夫に関する史料稿
― 『文学集団』への投稿を中心として ―
- 渡辺喜勝、
「雲居念仏」について
- 深井甚三、
近世中期の城下町人口動態について
― 信州上田城下町の場合 ―
- 斎藤吉雄・竹内彰啓・小林淳一・宇田川拓雄、
地方都市における“社会参加と生活の質”
東北文化研究室紀要通巻第17集
(日本文化研究所研究報告別巻第13集 1976年3月)
- 佐藤勉・鹿子木月子・谷田部武男、
農業構造改善事業と生産組織の形成
― 宮城県鹿島台町船越地区の事例研究 ―
- 大江篤志・菊池武剋・細江達郎、
老年期の社会化過程に関する社会心理学的研究
― 下北半島の一漁村の老年期を中心として ―
- 渡辺信夫、
史料 仙台藩寛永検地野帳(下)
東北文化研究室紀要通巻第16集
(日本文化研究所研究報告別巻第12集 1975年3月)
- 佐藤喜代治・加藤正信、
青森県東南部・岩手県西北部地方の言語調査報告
― 文法・語彙の部 ―
- 大内三郎、
押川方義と東北地方のキリスト教伝道
― その着手にいたる経過 ―
- 大藤修、
近世における農民層の「家」意識の一般的成立と相続
― 羽州村山地方の宗門人別帳の分析を通じて ―
- 斎藤吉雄・竹内彰啓、
“地域開発”におけるコミュニティーの機能
― 工業開発にともなう集落再編成の事例を中心にして ―
東北文化研究室紀要通巻第15集
(日本文化研究所研究報告別巻第11集 1974年3月)
- 佐藤喜代治・加藤正信、
青森県東南部・岩手県西北部地方の言語調査報告
― 音韻・アクセントの部 ―
- 大江篤志・細江達郎、
宮城県江島における青年期の社会心理学的調査研究
― 地理的に隔離された状況における「地域構造と青年期の適応空間」をめぐって ―
- 渡辺信夫、
史料 仙台藩寛永検地野帳(中)
東北文化研究室紀要通巻第14集
(日本文化研究所研究報告別巻第10集 1973年3月)
- 家坂和之・松下武志、
旧中間層の行動と意識
― 山中郷笹町の変貌 ―
- 楠正弘、
ゴミソ信仰とイタコ信仰
― 津軽の宗教 ―
- 渡辺信夫、
史料 仙台藩寛永検地野帳(上)
東北文化研究室紀要通巻第12・13集
(日本文化研究所研究報告別巻第8・9集 1972年3月)
- 佐藤喜代治・加藤正信、
三陸地方南部の言語調査報告
- 斎藤吉雄・佐藤勉・他、
集落再編成の社会的機能
- 渡辺信夫、
史料「三陸会議録」
東北文化研究室紀要通巻第11集
(日本文化研究所研究報告別巻第7集 1970年3月)
- 豊田武・遠藤巌・入間田宣夫、
東北地方における北条氏の所領
- 細江達郎、武井槇次、菊池武剋、
青年期の社会化過程に関する社会心理学的研究
― 資料 下北半島の青年期の追跡調査報告第9報 ―
- 細井計、
東北地方における海産物の流通と商人資本
― 三陸沿岸を中心として ―
- 亀田孜、
東北古美術雑話
東北文化研究室紀要通巻第10集
(日本文化研究所研究報告別巻第6集 1968年3月)
- 楠正弘、
イタコとオシラ神信仰
- 浜田直嗣、
仙台藩と江戸狩野
― その17世紀後半期に於ける提携について ―
- 工藤雅樹、
平安初期における陸奥国国府系古瓦の様相
- 入間田宣夫、
郡地頭職と公田支配
― 東国における領主制研究のための一視点 ―
東北文化研究室紀要通巻第9号
(日本文化研究所研究報告別巻第5集 1967年3月)
- 安倍淳吉・田中康久・石郷岡泰・大橋英寿・細江達郎、
下北半島における青年期の社会化水路に関する研究
― とくに準AおよびB型地域を中心にして ―
- 難波信雄、
幕末における仙台藩の国産統制
― 幕末藩政改革プランの前提 ―
- 田代脩、
戦国期における伊達氏の段銭帳
東北文化研究室紀要通巻第8号
(日本文化研究所研究報告別巻第4集 1966年3月)
- 亀田孜、
周継雪村の瀟湘八景図
- 佐藤喜代治、
岩手県三陸地方北部の言語調査報告
- 竹内利美、
東北村落と年序集団体系
- 月光善光、
箆峰寺開創と十一面観音信仰
- 細井計、
仙台藩中期における新百姓の自立過程
― 畑作山間地帯の例として ―
- 豊田武・加藤優、
『晴宗公釆地下賜録』とその考察
東北文化研究室紀要通巻第7号
(日本文化研究所研究報告別巻第3集 1965年3月)
- 家坂和之・田代不二男・江田忠・山田敬道・佐藤勉・佐藤嘉一・守屋孝彦・船津衛・志田直正・山崎達彦、
米沢買継商の精神構造
- 亀田孜、
中尊寺供養願文雑事
- 豊田武・田代脩、
中世における相馬氏とその史料
(史料)相馬関係文書
- 細井計、
東北文化研究室の沿革
東北文化研究室紀要通巻第6集
(日本文化研究所研究報告別巻第2集 1964年3月)
― 平泉文化の研究 ―
- 矢島羊吉、
観光の辞
- 高橋富雄、
平泉政権の成立とその権力構造
- 大塚徳郎、
平泉を中心とする古代東北の交通路
- 金倉円照・松山善昭、
東北地方における天台教団成立の独自性
― 平泉諸寺院を中心として ―
- 石田一良、
中尊寺建立の過程にあらわれた奥州藤原氏の信仰と政治
- 梅沢伊勢三、
平泉文化と鎌倉文化
― その歴史的関連と性格的相違 ―
- 飯田須賀斯、
金色堂の建築について
- 板橋源、
平泉中尊寺正応元年棟札考
- 豊田武、
平泉史料補遺
東北文化研究室紀要通巻第5集
(日本文化研究所研究報告別巻第1集 1963年3月)
- 石津照璽、
発刊の辞
- 佐藤喜代治、
秋田県米代川流域の言語調査報告
- 家坂和之・佐藤勉・高橋勇悦・八木正・佐藤嘉一、
地方都市における市会議員の活動と住民組織
- 小西健二、
幕末期における一地主の経営
― 岩手県和賀郡上小山田村一の倉家の場合 ―
- 細井計、
近世東北農村の構造と煙草生産
― 仙台藩登米郡河原村の場合 ―
- 豊田武・佐藤宏一、
陸前新宮寺文殊堂所蔵一切経の奥書
東北文化研究室紀要通巻第4集(1962年3月)
- 豊田武、
東北中世の修験道とその史料
- 家坂和之・高橋勇悦、
都市周辺の人口移動
― 宮城県七ヶ浜町、利府村の事例 ―
- 渡辺信夫、
給人地方知行制下の貢租形態
― 元文三年の南部藩「諸士知行出物諸品并境書上」の分析(一)
- (史料目録)岡田重精、東北大学所蔵羽黒修験関係資料目録
- (史料)石川文書
- (史料)八槻文書
東北文化研究室紀要通巻第3集(1961年3月)
- 石津照璽、
東北のおしら
- 堀一郎、
湯殿山系の即身仏(ミイラ)とその背景
- 佐藤喜代治、
北奥方言と南奥方言の境界地帯における動詞の活用について
- 塚本哲人・佐藤勉・高橋勇悦・八木正、
慈恩寺開創と葉山信仰
- 渡辺信夫、
「給人」地方知行と村に関する一試論
- 鎌田永吉、
解説「千葉家文書」目録
― 明治中期一地方資本の存在形態 ―
- 千葉家文書目録
東北文化研究室紀要通巻第2集(1960年3月)
- 豊田武、
東北山村の調査
- 平重道、
東磐井郡の概要と総合調査の意義
- 鎌田永吉、
近世後期における東北山村の史的展開 ― 旧仙台藩東磐井郡鳥海村の場合 ―
- 渡辺信夫、
村方地主の成立とその構造
― 岩手県東磐井郡金家の場合 ―
- 塚本哲人・江馬成也、
家族生活の分析
― 一農民の生活史を通して ―
- 吉田裕、
村落構造と指導者の性格
- 松山善昭、
東北地方農村における仏教受容の特殊性
― 岩手県大東町丑石部落を視点として
- 岡田重精、
丑石の祭祀と儀礼
― 特に部落構造との連関性 ―
- 佐藤正順、
東北地方の宝根山信仰
- 亀田孜、
岩谷堂・松岩寺の阿弥陀銅像〔写真解説〕
文化 第22巻第4号 東北文化研究特集(1958年7月)
- 豊田武、
東北農村文化の総合的研究
- 佐藤喜代治、
福島県方言の敬語法
- 金谷治、
会津藤樹学の性格
- 岡田重精、
部落構造と儀礼
― 宮城県大島字崎浜の場合
- 松山善昭、
講の起源と変遷
― 特に東北地方における真宗の講の発達について ―
- 飛田昭、
亜欧堂田善について
- 森口隆次、
福島・岩手の和紙漉に見る陸奥紙の伝統
- 江馬成也、
契約講について
― 三陸南部小漁村の場合を通じて ―
- 斉藤吉雄・田野崎昭夫、
相馬地方に於ける農村の社会慣行
― 家族と部落の構造と慣行の分析 ―
- 鎌田永吉、
奥羽諸藩における長崎俵物の統制
|