
リンクは自由!
『La Movado』第710号(2010.4), 711号(2010.5), 712号(2010.6), 713号(2010.7)掲載文に加筆
「1.はじめに」ヘ

詩人土井晩翠と八枝夫人の長男、土井英一の多方面にわたる活動については、拙著『エスペラントを育てた人々 ―仙台での歴史から―』のうち、「寄付金つき切手の生みの親 ―土井英一―」において比較的詳しく扱った。彼がエスペラントなどでの国際文通をきっかけに寄付金つきの慈善切手を日本にも導入することを思いつき、その制度を詳しく調査して実現に努力したこと、そしてそれが死後の1937年に愛国切手として実現したことなど、大筋としてはこれまでも知られていた。拙文においては、当時の史料を見直すとともに逓信省側の事情などを分析して、民間航空事業助成のための愛国切手として発行されるに至った経緯を中心に、さらに明らかにできたと思っている。
しかし、英一のこの活動のハンセン病との関わり、および周囲に及ぼした影響の大きさについては、十分に扱うことができなかった。本稿ではこの観点からの考察を加えたい。
英一が慈善切手の提案を初めて公にしたのは、1930年10月9日づけの『東京日日新聞』に掲載された投書であった。ここには慈善切手発行の目的として、「まづ第一にその数多き点において列国中に比を見ざるわが癩病患者の救済問題」と明記されている。彼がこの時点でまずはハンセン病患者の救済を慈善切手の目的に考えていたことは間違いない。

しかし、それが彼が想定する唯一の目的であったとまで断定することはできない。むしろ一例として挙げているだけのようである。英一にはハンセン病に関して具体的な体験があったことは知られていない。彼がこの問題を意識したのは、おそらくは教会ないしYMCAでの活動を通してのことであり、観念的な関心にすぎなかったであろう。
周囲の人の回想からは、英一が慈善切手の目的としてほかに「結核患者救済」「社会改善」「凶作救済」なども考えていたことが伝わってくる。投書の「一団体の義捐金募集に比べて遥に普遍的であり民衆的」、「この切手を貼つた手紙が全国津々浦々に行きわたる時、それは全国民の公共心を刺戟せずには止まないであらう。」という文からは、英一の念頭には博愛精神の発揮というもっと一般的な目的があったように理解できる。
とはいえ、「癩病患者の救済問題」と記されていたことから、英一の投書はハンセン病関係者の関心を呼んだのであろう。直ちに日本MTLの機関誌『日本MTL』11(1930.10)に転載された。日本MTLは、1920年代、キリスト教の立場からさまざまな社会事業に取り組んだ賀川豊彦を中心に結成された「救癩」団体で、光田健輔をも理事に迎えて、彼が主唱する絶対隔離政策を側面から推進する働きをするものであった。
宮川量(みやかわはかる)は、英一の慈善切手活動のことを知り、1931年から32年にかけて共通の知人を介して英一と連絡をとった。仲介したのは、少年期から旧制高校まで仙台で過ごし、東大で生物学を研究したのち、京都でキリスト教の伝道に専念していた服部治であった。宮川は英一と文通を重ねて意気投合する。キリスト教とエスペラントを共通項として感じたと思われる。宮川との接触によって、英一の中でも慈善切手の目的として「救癩」の比重が増していったのだろう。
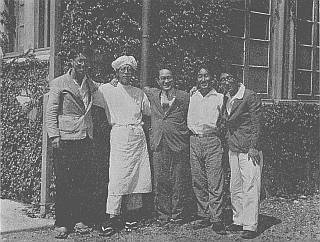
前節で触れたように、1931年3月に国立の長島愛生園(岡山県)が開設されて、光田と林文雄、宮川、および医師の田尻敢(いさむ)やのちに林と結婚する大西富美子らは全生病院から愛生園に異動していた。
愛生園でも、当初は多少なりともエスペラントを継続しようとする試みがあったようだ。しかし、全生エスペラント・クルーボに匹敵するほどの熱心なエスペラントの学習活動にはならなかったように見える。
『悲惨のどん底』の訳者黒川眸も、患者の中から「開拓者」として選ばれて愛生園に移っていた。青年団を率いたらしいが、その標語として採用されたのは、全生エスペラント・クルーボのそれ、Venis, Vidis, Venkis.であった。黒川は1932年11月、遺著『歌集新しき住家』(長崎書店, 1933)を遺して病死した。全生エスペラント・クルーボ時代の歌「スリツパの音近づきて扉に現(あ)れし指導者(グヴィダント)塩沼ほがらかに笑ます」「病めりとし思ふ心のいつしかに教室に来れば忘れてありぬ」なども収録されている。林が塩沼に黒川の臨終の様子を伝えた手紙は『日本MTL』23(1933.1)に掲載された。異例の扱いとも言えよう。
林は、ハンセン病専門の学術雑誌『レプラ』3巻(1932)にエスペラント書き論文「癩に於けるRubino氏反応」を寄稿している。少し時間を置いて同誌6巻(1935)には、大西のエスペラント書き論文「眼瞼結膜に発生せる癩腫」が掲載された。また田尻の5巻(1934)掲載論文「呼吸器の癩(第2報)鼻の癩」、6巻掲載論文「呼吸器の癩(第3報)口腔、咽頭及び喉頭の癩(附、食道の癩)」にはエスペラント文抄録が付けられている。医師の側でのエスペラントへの関心は継続していたことになる。なお、それに呼応するかのように、全生病院に残っていた塩沼英之助も同誌6巻掲載論文「癩盲人の統計的観察並びに全身症状の消長と眼疾初発との関係」の抄録をエスペラントで書いている。
宮川とエスペラントの関係はあまり具体的には分からない。全生病院へは就職以前から出入りしていて、『山桜』1929.2に前任者の広畑隣助を追悼する文を寄稿している。その中で「その時院長さんのおたくでエスペロのレコードを広畑さんと一緒に聞いたんだつた。エスペラントで一二回僕はお便りをさし上げた事があつたが、その返事はいただかなかつたと記憶する。」と回想していることから、それまでにエスペラントの学力をつけていたであろうことは分かる。
塩沼によれば、宮川も全生エスペラント・クルーボで熱心な「後援者」であったとのことである。教室での直接の指導というより、側面からの協力であったのだろう。例えば、宗近真澄が RO 1930.9に寄稿した訪問記「全生病院を訪ねて」には「…見ると立札にFlorĝardenoと書いてあり、dalioやlilioとEsperantoで書いた小い木の名札が沢山に立ててある。まるでEsperantujoに来た様である。」と院内が描写されているが、これは宮川が行ったことと考えられる。また、宮川が代表者として武蔵野歌会の名義で刊行した歌集『東雲のまぶた』(長崎書店, 1930)には、全生病院でのエスペラント活動への言及が多い。
宮川は本業の農園指導のかたわら、日本におけるハンセン病の社会史を研究しており、のち『レプラ』6巻には「救癩史蹟西山光明院に就いて」を、7巻(1936)には「鎌倉時代に於ける癩救済者忍性律師の研究」を掲載する。いずれも古文書と遺跡とを詳しく調査してまとめた本格的な歴史研究である。それぞれ1ページほどのエスペラント文抄録が付けられているが、宮川が書いたエスペラント文で今に残るのはこれだけであろう。多少の誤りを含むが、おおむね文意はとれる。
宮川は英一の慈善切手運動のことを知ると、長島に伝えて、関心を呼び起こした。光田園長は長島愛生園を隔離に基づく「癩の根絶」のための拠点にすべく活発に動いていた。定員を超えてまで患者を収容していたため、維持費や患者住居建設費として財界や広く一般から寄付を募る必要があった。慈善切手は、「救癩」問題への国民の関心を高め、寄付金を得るための願ってもない手段と見えたであろう。なお、宮川の証言によると、「愛国切手」という名称は林の発案に基づく。
宮川は自身の立場から「救癩」目的の愛国切手発行に向けた運動を進め、『日本MTL』28(1933.6)に「癩なからしむるための資源 愛国切手運動提唱」を寄稿した。この前後の同誌にはこのほかにも関係の無署名記事がたびたび掲載されているが、宮川の計らいによるものである。

英一は、病気療養のため東北大学を休学したまま、慈善切手の実現を見ることなく、1933年9月に死を迎えた。英一の訃報は『日本MTL』32(1933.10)で伝えられ、さらに35(1934.1)には宮川の「愛国慈善切手運動の提唱者 土居[ママ]英一兄を憶う」(「10月11日稿」と注記)が掲載されている。「人生の価値が量でなく質によつて決定さるものとしたら。我が友故土居[ママ]英一兄の如きは若くして逝きしといへ人生に大きな足跡をのこした。尊むべき戦士である。」と書く。英一と宮川とは結局一度も会うことはなく、文通のみによる交流であった。
前年の長女に続いて長男をいずれも二十代半ばで失ったことは、晩翠夫妻にとって大きな打撃であったが、英一の遺志の達成に尽力することでその衝撃を昇華したと言える。ドイツへの分骨と小泉八雲記念碑の建設、およびエスペラント運動への支援などについては拙著で触れた通りであるが、両親はまた「救癩」問題への関心を深めていく。
英一の死後、宮川は晩翠夫妻との間に文通を続けた。英一は慈善切手実現に向けた政府との交渉において、父晩翠の友人で衆議院議員の内ヶ崎作三郎を頼みにしていたが、それを引き継いで宮川も内ヶ崎に働きかけを行った。これには晩翠の仲介があったようだ。晩翠はこのほかにも広い人脈を生かして宮川の活動を助けた。
また林も、冊子『日本の奴隷解放 附愛国慈善切手運動提唱』(1934)を日本MTL長島支部パンフレットとして刊行した。「[英一]氏の遺志を継ぎその実践によつて一つは英霊を慰め、一つは我国数千年来の問題を解決」するため「癩救済の資源」として提唱するとされている。国際連盟の依頼で行ったハンセン病事情視察の世界旅行(1933〜1934)での見聞に基づいて、との理由づけも見られるが、これはいささか疑わしい。
英一の母八枝は生地高知での滞在から仙台への帰路、1935年10月27日に愛生園を訪れる。この訪問については仙台を発つ前に宮川と打ち合わせていたようだ。患者への講話では当然のこととして英一のことに触れており、職員らとの間でも話題に上った。患者たちにも英一の活動のことは以前から知られており、訪問は心待ちにされていた。また、八枝自身が患者にとって「日頃御手紙で、私達の悩みの御相談相手と成つて」(『愛生』1936.1)いたという事情もあったらしい。
八枝はさらにその足で、雑誌『主婦之友』の依頼により神山復生病院(静岡県)も訪問した。1936年1月号に寄稿した訪問記の中で、病院の様子を伝えるとともに、英一の活動を紹介し、「患者全部収容できる病院設備」の費用を賄うための愛国切手制度の導入を読者に呼びかけている。この訪問の後、八枝は愛生園と復生病院に折にふれて慰問の品を送り続ける。
愛生園は医師小川正子を四国などに派遣し、患者の収容にあたらせていた。1936年1月の高知県出張では、八枝の母校である県立第一高女で講演するよう園の幹部から指示があった。前年の八枝の訪問時には直接言葉を交わすことのなかった小川だが、これをきっかけに八枝に手紙を出して、親交を結ぶようになる。小川の患者収容活動を感傷的に描いた手記は、園誌『愛生』1936.2「四国の癩を救へ」特集に、八枝の寄稿とともに掲載されているが、ここには「第一高女は彼の救癩運動の隠れたる真実な援助者理解者であられた若き故土井英一氏の母上の母校で」との言及も見える。

内ヶ崎が提起した国会での建議が実って、1937年6月に日本初の寄付金つき切手として愛国切手が発行された。逓信省内部の事情から、寄付金の使用目的は民間航空事業助成となっていた。寄付金つき切手が実現したことは、関係者にとって喜びではあった。八枝は一番に郵便局に出向いて買った切手を手にして、英一が資料整理にタイプライターに向かう姿を思い出しながら、嬉し涙を流したとのことである。
しかし、「救癩」目的の切手を願望していた長島の人々にとって、これは一歩前進ではあるにしても、むしろ不本意な結果であった。光田は逓信相に直接手紙を送って、また林は『愛生』誌上で、それぞれ強い抗議の意思を表明する。
小川の患者収容活動の手記はまとめて単行本『小島の春』(長崎書店, 1938)として出版された。晩翠夫人として、また、自身でも文筆家として名の通っていた八枝から跋文を寄せてもらっている。この本はベストセラーとなり、のちに映画化もされるほどに評判をとった。「救癩」への一般の関心を高めるには十分な効果があった。
このころには当時の社会情勢の中で「救癩」目的の寄付金つき切手の実現の可能性は薄くなり、それにつれて語られることも少なくなっていく。それでも、晩翠夫妻はハンセン病への関心を失わなかった。
宮城県に新しく国立療養所東北新生園が設置されると、晩翠夫妻は開園式から間もない1939年12月28日に早速訪れて、入園者に講演を行っている。他の折に訪問したこともあったようだ。晩翠は新生園訪問の思いを「逝ける子の願をつぎて病む人の慰めたらむかずならぬ身の」と歌に詠んで書き置いた。「逝ける子」とは、もちろん英一のことである。
新生園園長鈴木立春も古いエスペランティストで、第12回日本エスペラント大会(仙台, 1924)の準備委員であり、1926年の日本エスペラント学会会員名簿に名前が載っている。詳しくは分からないが、当時から晩翠と知り合いであった可能性は高い。そのような縁もあってか、晩翠は新生園の園歌を作詞したほか、鈴木の退任(1948)までの間関係が続いていた。なお、鈴木の前任地、第二区道県立北部保養院(青森、現国立療養所松丘保養園)の院長中條資俊(なかじょうすけとし)もエスペランティストであったことが知られている。
八枝は、英一の思い出ほかの書き溜めていた文章をまとめて、『随筆 藪柑子』(長崎書店, 1940)として刊行した。今度は『小島の春』の時のお返しに、有名になっていた小川から跋文を寄せてもらっている。その中で小川は愛生園での初めての出会いを思い起こしている。「直接に御話を伺つたり御接待に出たりしたのではなかつた。…… 然し……御子息英一様の救癩愛国切手の御計画に就いても、前々から伺つて居た事であり、夫人の最初の御来園は種々の意味で、其の頃の私に深い印象として残された。」のち1943年、小川正子の死に際して、晩翠は日本救癩協会(日本MTLの後身)の機関誌『楓の蔭』145(1943.6)に「小川正子女史を弔ふ」の詩を寄せて、その死を悼んだ。
英一が慈善切手のための活動をした時代、日本のハンセン病対策は転機にあった。彼の新聞投書の翌年、1931年に成立した癩予防法によって、隔離政策は決定的に強化される。行政の権限が強められ、患者の救済より「民族浄化」が強調されていった。光田は、ハンセン病分野の第一人者として絶大な発言力を得て、絶対隔離政策を強力に推進する立場に立ち続けた。英一の慈善切手の発意が善意に基づくものであったことは疑いないが、本当にハンセン病患者の救済に役立つように使われる状況であったかどうか、残念ながら、疑問の残るところである。
愛国切手について内ヶ崎は、「英一君の理想の、慈善事業にまでは、必ず私の手で、近き将来に於て実現するやう努力したい」との希望を持っていた。しかし、寄付金つき切手が英一のもともとの希望により近い形で実現するのは、戦後1947年11月の社会事業共同募金切手の発行によってである。その時には内ヶ崎もすでにこの世にいなかった。
copyright GOTOO Hitosi 2010-2011
著作権法規に則って利用することができます。
「エスペラントとは?」のページに戻る
後藤斉のホームページに戻る