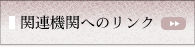��980-8576
�{�錧���s�t����27��1�� ���k��w��w�@���w�����ȍ���w�������� �d�b�F 022-795-5987�E5988 FAX �F 022-795-5988 ���k��w���w�� ��w�@���w�����ȍ���w������ |
|
| �����g�D�F | ���с@���i���k��w��w�@���w�����ȋ����j |
| �֓��@�ϖ��i���k��w��w�@���w�����ȋ����j | |
| ��@��v�i���k��w��w�@���w�����ȏ������j | |
| �����@�m�i�{�鋳���w�����j | |
| �|�c�W�q�i������w���u�t�j |
���ɁA���̎����ɂ��ďЉ�܂��i�ȉ��A�|�c�W�q�쐬�j�B
�ꕔ�A���̎�������菑���ō쐬���������n�}������܂��̂ŁA�����������B
�P�D�͂��߂�
���̒����́A1940(���a15)�N���A���k�鍑��w���� ���эD�����i���₵ �悵�͂�1888�|1948�j�ɂ���čs��ꂽ���k�����̒ʐM�����ł��B���̈ꕔ�́A�����w���k�̕����x�i1944(���a19)�O�ȓ��j���ɔ��\����č����]���܂������A�S���ʂ̔��\���҂���钆�A����1948(���a23)�N�ɐ����Ȃ����܂����B���k��w�ݐE���̐����ł��������߁C�����̎����͓���w���w������w�������Ɉ����p����邱�ƂƂȂ�܂����B
�����ł́A���эD�����̒�����A�w�p�x���c�̂ɒ�o���ꂽ���̕��A���k��w�ɕۊǂ���Ă��钲���[�ⓝ�v�\�Ȃǂ����ƂɁA���̎����̑S�̑����Љ�܂��B
�Q�D���k�������z�����̑���
�Q.1. ���эD�����̗����E�Ɛ�
���эD������1886(����19)�N�A�����ɐ��܂�A���������t�͂��o�āA1922(����45)�N�ɓ����鍑��w�����w�Ȃ𑲋Ɓi���͍���w�j�A���m��w�E�������q��w�Ȃǂ��o�āA1934(���a9)�N�ɓ��k�鍑��w�ɕ��C�B�����ɂ́A�w����w�T�_�x(1930)�A�w����w�̏����x(1941)�A�w�W����@�����x(1922)�A�w���ꍑ���@�v�`�x(1927)�A�w���{���@�j�x(1936)��������܂����A�����̂قƂ�ǂ͓��k�鍑��w�ɕ��C����O�Ɏ��g�܂�Ă����悤�ł��B���k��w���C��͉��H�����̒����E�����ɓw�߁A�w���k�̕����x(1944�A�O�ȓ�)���܂����A1948(��23)�N2���A���N3���̒�N�ފ���ڑO�ɋ}���Ȃ����܂����B�Ō�̒����ƂȂ����w������b�{�I�����x�́A��e�ɋ��s��w�֒�o����Ă������m�_���̏͂������A1950(���a25)�N��g���X����o�ł��ꂽ���̂ł��B
�Q.�Q. �����̊T�v
(1)�����̖ړI
�����̖ړI�ɂ��āA���эD�����̕��ɂ́u�Â�����̉��C�A��b�A��@�𑽕��Ɉ⑶���铌�k���������đ��̑S�e�𖾂ɂ��j�I�����Ɏ�����Ƌ��ɛ����̚���{���݂ɛ����鎑�ނ̏[�����Ƃ��(�w���ƕxp71)�v�ȂǂƂ���A����n���w�I��@�ƕ�������j�I�����ɂ���ē��{��̗��j���𖾂���Ƃ����ړI���f���܂��B�܂��A�����҂ɑ��钲���w���i��P��A��R��̒����[�\���́u�L���@�v�ɂ��j�ɂ́A�u���N���ɑ��k���ď����ĉ������v�Ƃ��邱�Ƃ���A�`���I������Ώۂɂ��Ă������Ƃ��킩��܂��B
�����̂��Ƃ���A�����̒��ڂ̖ړI�́A���k�n���ɂ�����`���I�����̕��z�c���ɂ������ƍl�����܂��B
(2)�����̕��@
���̒����́A���эD����������@�ւɒ������˗����A�������ʂ��L�������������[���������܂����B�����̒����[�ɂ͐܂肠�Ɓi�c�ɓ�܁j�Ȃǂ����邱�Ƃ���C�L����͑命�����X�ւɂ���ĉ�����ꂽ�ƍl�����܂��B
�������˗����ꂽ����@�ւ́A�q�퍂�����w�Z�i1941(���a16�j�N�x�̂ݍ����w�Z�B���k�n���ɐݒu���ꂽ�{�Z�̑����͖�2400�`2600�Z�j�A�e���̒j���t�͊w�Z�i�S6�Z�j�̂����A�قڑS�Z�ŁA���̂����X���قǂ��璲���[���������Ă���Ǝv���܂��B
�����[�́A�T���v���̂悤�Ȃ��̂��p�ӂ���܂����B����͑�P��̒����[�ł����A�\���̏�i�ɁA�n���A�����Ҏ����A���ߐ��������܂��B���i�ɁA�L���@�i�����̕\�L�A�g�p���ʁA�Q�l��̎g�p�@�A��`�̐V�ÁA�g�p�҂̔N��j������A����͎�����̒����@�̎w���ɂ�����ƍl�����܂��B
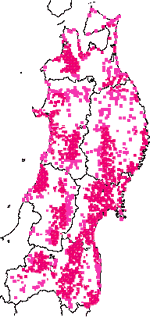
�}4�@�����n�_�ꗗ
�܂��A�����[�̖{���́A�T���v���Ɏ������悤�ɁA�ォ��ANo.�W��A�Q�l������A�����L�������p�ӂ���Ă��܂��B�u�W��v�̐��́A��P��F97�A��Q��F67�A��R��F100�A���v264�ɂȂ�܂��B���̂����A�������ꌤ�����w���{����n�}�x�S6����300����64���A�w�������@�S���n�}�x��1�`5����270����40���Ƌ��ʂ��钲�����ڂ��܂܂�Ă��܂��B���эD�����̋L�q�ɂ��ƁA�u���k�����ɓ����̂����b������݁c�i�w������������x9,p75�j�v�A�u�����ʂ̏��������̂Ś���̗��j�I�����Ɉ킷�ׂ��炴����ɌÂ���b�A����̐��Ԃ�m��ɕK�v�Ȕ��Ɍ`�̝̂���b�A����Ȃ��̂Ɍ�b�{�I���ۂƂ��ęJ�l�̑傫�����̂�����B(�w������b�{�I�����xp21)�v�Ƃ���܂��B�܂��A�����[�̍��ڂ́A���C�E��b�E���@�ȂǑ���ɂ킽���Ă��܂����A���ꂼ��̕����̌n�I�ɖԗ����邽�߂̍��ڂ��p�ӂ���Ă���킯�ł͂���܂���B�����̂��Ƃ���A���̒����[�ł́A��ɓ��k�����ɓ����I�Ȍ`���邽�߂̍��ڂ��p�ӂ���Ă����ƍl�����܂��B
�����n�_�ɂ��āA�n���̈قȂ�𐔂����2000�قǂɂȂ�A�l����ʐςɑ���n�_���́A���ɍ����ƌ����܂��B�������w���{����n�}�x�w�������@�S���n�}�x�ȂǂƔ�ׂ�ƁA�����\�̂悤�ɂȂ�܂��B�����̒n�_���ꖇ�̒n�}�ɔz�u���Ă݂�ƁA�}�S�̂悤�ɂȂ�A�n�_�����ݍ����A�n�}���̍ۂɍH�v���K�v�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B
�\�@�����n�_���ƒn�_���x�i�����ρm���k�n���̑S�n�_���n�j
|
�����ҁi�����[�̋L���ҁj�ɂ��ẮA���w�Z�E�����w�Z����̒����[�ɂ́A�����[�\���Ɋw�Z���E�w�Z��A�u���v��ȁu�Ǖ��������v�Ȃǂ̋L����A�Z���E�P���ȂǁA��E���̋L��������܂��B�܂��A�t�͊w�Z����̒����[�ɂ́A�u�ꕔ��N�v�u�b��N�v�ȂNJw�N�̋L����A�u�`�q�v�ȂǁA�������s���n�߂����O���݂��܂��B�����̂��Ƃ���A�����҂́A����60��`10��㔼�i����15�N���`�吳�����܂�j�̕��L���N�w�̒j���Ǝv���܂��B�����[�̕\���◓�O�ɁA���������̏Љ�A�ǒ����̐\���o�A�u���\�����m�������S���܂��v�ȂǂƂ��邱�Ƃ���݂�ƁA�����҂͕����ɋ����������A�����ނˋ��͓I�ł������Ǝv���܂��B
���ۂ̉҂́A�����[����͂͂�����c���ł��܂���B�������A����@�ւɈ˗��������R�ɂ��āA���эD�����́u�y�n�̐l�Ŏ����̋����ł��邽�ߏ��{�Z���͈��ƂȂĂ��Ɖ]�Ӑl���r�������B�i�w������b�{�I�����xp22)�v�Əq�ׂĂ��܂��B�܂��A�ꕔ�̒����[�Ɂu�����҂͓��s�̓y���l�ɂĎ���g�p�����錾����L����v�ȂǂƂ��邱�Ƃ���A�����҂͎�����̉҂����˂��ꍇ������Ɛ�������܂��B
�R�D�����̈Ӌ`
�R.1. �w�j�I�ʒu�Â�
���{�̕����n���w�������n���ǗY(2002)�w20���I�ɂ�������{�̕����n���w�����x(p23)�́C���эD��(1950)�w������b�{�I�����x����{�̕����n���w��Ɉʒu�Â���L�q�ɂ����āC�n���w�I���@�ɉ����A���������Ƃ̑Δ���d���A���̎��H���s���Ă���_�ɓ��F��F�߁A��������j�w�ƕ����n���w�̗Z���Ƃ����V���������̌�����͍������_��]�����A���k�̕����n�}�����Ȃ����Ƃ��^�⎋���Ă��܂��B����@��(1993)�w�����n���w�̓W�J�x(p26�`27)�ɂ����l�̎w�E������܂��B���̒����́A�n�_�����c��ł��邽�߁A�����̒n�}���͑����ɍ���ł������Ǝv���邪�A�u���v�\�v�ɂ���Ă����܂��ȕ��z�ƒn�捷���������Ƃɂ͐������Ă����Ƃ݂��܂��B
�R.2. �����̗��p
���̎����𗘗p���ċL�q���ꂽ�_���ɂ́A���̂悤�Ȍ���������܂��B
![]() ���k�����̊T���F������㎡(1961)�u���������̌�b1�@�k�C���E���k�v�A�������`(1981)�u���k�����̌�b�v
���k�����̊T���F������㎡(1961)�u���������̌�b1�@�k�C���E���k�v�A�������`(1981)�u���k�����̌�b�v
![]() �����Ƃ̑ΏƁF�������M�E�������`�E�O�c�x�Q(1988)�w�����ɐ�����Ì�x��_��
�����Ƃ̑ΏƁF�������M�E�������`�E�O�c�x�Q(1988)�w�����ɐ�����Ì�x��_��
![]() ���荀�ڂ̍l�@�F�^�c�M��(1973)����k�n���ɂ�����w���Ȃ��x�Ɓw�����x�̕������z�Ƃ��̉��߁\�\�� ���эD�����m�̒���������n�}�����ā\�\�v�i��R��̒����ɂ��āA�T�v�̋L�q������j
���荀�ڂ̍l�@�F�^�c�M��(1973)����k�n���ɂ�����w���Ȃ��x�Ɓw�����x�̕������z�Ƃ��̉��߁\�\�� ���эD�����m�̒���������n�}�����ā\�\�v�i��R��̒����ɂ��āA�T�v�̋L�q������j
![]() ����n��̍l�@�F����돺(1978)��ɒB�E�암�ˋ��ɂ����铙����̐��ڣ�Ȃ�
����n��̍l�@�F����돺(1978)��ɒB�E�암�ˋ��ɂ����铙����̐��ڣ�Ȃ�
��N�̒������ʂƂ̔�r
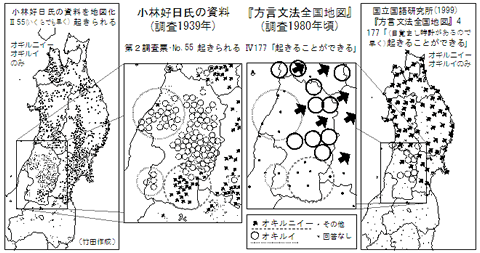
�������̒n�}�쐬�ɂ́A�������ꌤ������HP�Ō��J���Ă���f�[�^�ƃv���O�����𗘗p���܂����B
�L���Ċ��Ӑ\���グ�܂��B
�}6�@�����̗��p
���эD�����̎����̑�Q�����[�E�W��No.55�u�i������ł������j�N������v�̉��W�v���A�n�}�������݂܂����i1500�n�_�j�B�R�`���̕��z�ɒ��ڂ��āA�w�������@�S���n�}�x��177�}�u�i�ڊo�܂����v������̂ő����j�N���邱�Ƃ��ł���v�i���k�S���149�n�_�j�Ɣ�r������}�̂悤�ɂȂ�܂��B
�R.3. �����̈Ӌ`
���̎������₳�ꂽ1950(���a25)�N��ȍ~�C�w�E�ł͒������ɂ��Ւn�ʐڒ������d���C�ʐM�����œ�����i�P�����Ă��Ȃ���ʂ̐l�̉��������ɂ��j�͌y����X���������Ă��܂����B�^���@�≹���L�������y�������Ƃ�����C��萳�m�Ȍ���`���邽�߂̊w��I�葱������������C���ꂪ�d�v�����ꂽ���Ƃ͓��R�̂��Ƃƍl�����܂��B�������C���̒�������60�]�N���o������ł́C���{�S���ŕ����̐��ނ������ł���C�`���I�����̋L������������܂��B���̐�C�����ɐi�������^���@���p���C�H�v���Â炵���������s�����Ƃ��Ă��C���̎����Ɠ����̕����ʂ������邱�Ƃ͓�x�ƂȂ��ł��傤�B���ł�ڑO�ɂ�������̋L�^�����Ƃ��āC���̎����̓��e�����߂Č�������K�v������܂��B
���Q�l���������эD�������g�̕� �������M�E�������`�E�O�c�x�Q(1988)�w�����ɐ�����Ì�x��_�� |