|
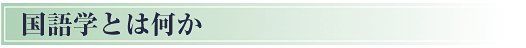
― 国語学とはどのようなことをする学問なのでしょうか。
教授 国語学は日本語を研究する学問分野です。日本語の研究ですから、日本語学ともいいます。
― 研究するというのは、わからないことを明らかにすることだと思うんですが、でも、日本語はふだんから不自由なく使っていますから、わからないことなんてないように思います。
教授 たしかに、われわれはふだん日本語を自在にあやつっていて、とくにわからなくて困るといったことはないかもしれません。でも少し考えてみると、簡単にはわからないことはたくさんあります。たとえば、次のようなものはどうですか。
(1) 彼は教科書を読むと眠くなる。
(2) 彼が教科書を読むと眠くなる。
この二つの文は、「は」と「が」が違うだけなのに、「眠くなる」人が違いますね。(1)は眠くなるのは「彼」ですが、(2)は、彼が読んでいるのを聞いている人ではありませんか。では、なぜこうなるのかわかりますか。
― そういえば、たしかにそうですね。どうしてこうなるんですか。
教授 これは、「は」と「が」のはたらきが違っているからなんですね。本当はもっと複雑なんですが、きわめて簡単にいえば、「は」は文の最後まで支配力が及ぶのに対して、「が」はそうではないということです。
― なるほど。たしかにわからないことがあるんですね。そういえば、ことばの研究・分析といえば、「文法」が思い出されます。いまみたのも文法のような気がしますが。
教授 そうですね。いまみた「は」と「が」のような問題について考える分野を文法論といいます。たしかに文法論もことばの研究の一部です。ただ、それだけではなく、発音の問題やことばの意味の問題などもことばの分析です。たとえば、「てんぷら」(天麩羅)と「てんどん」(天丼)の「ん」はそれぞれ発音のしかたが違うのがわかりますか。
― あっ、「てんぷら」の「ん」は違うような気がします。これだけ唇を閉じて発音していますね。なるほど。ふだん使っている日本語にも気がつかないことが多くあるようですね。
教授 このような発音を研究する分野を音声学・音韻論といいます。また、語の意味を研究するような分野は意味論といいます。実は、人はことばを使うときには無意識に一定のルールやしくみにしたがっているんです。そのようなルールやしくみを明らかにするのが言語の研究で、とくに日本語を対象とするのが国語学なんです。
― ところで、日本語といっても、古典のことばも日本語ですね。こういうものも研究するんでしょうか。
教授 日本語といってもいろいろな日本語があります。古典のことばは日本語の歴史的な姿の一面です。古典のことばが次第に変化して、現代の日本語になったんです。古典のことばと現代のことばの間の姿がみられる資料がありますから、そのようなものを利用すれば、日本語の歴史がわかります。これも国語学の一分野です。
― それから方言も日本語だと思うんですが。
教授 もちろん地域のことば、すなわち方言も学術的な研究の対象になります。地域のことばの研究は、その実際にことばが話されている地域に行って、方言話者の協力を得て、調査します。もちろん、これも国語学の一分野です。ですから国語学は、日本語であれば、どのような日本語であっても研究の対象になるといえます。
― なんとなく、国語学という学問が何をやっているか、わかったような気がしてきました。
教授 日本語にかぎりませんが、ことばには、かくれたしくみや使用の規則があります。そして、あらゆる日本語を対象にして、日本語のしくみや規則を明らかにしようとするのが国語学なんです。ただ、ここで説明した内容はごく一部ですから、もう少しはっきりさせるためには、関連の本を読んでみるといいでしょう。また、学生の卒業論文の題目をみても、国語学のイメージはつかめるのではないでしょうか。
― わかりました。どうもありがとうございました。
|